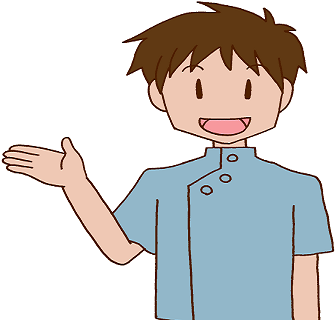テルモの殺菌灯販売契約拡大とその背景にあるもの
Terumoは2017年01月06日にXenex社の紫外線殺菌ロボットLightStrikeの日本での独占販売契約を締結した。
引き続き2018年に、シンガポールにおいても公的および私的医療施設にLightStrikeロボットを提供するという契約を広げている。
なぜ今更殺菌灯?と思われるかもしれない。
今から約20数年前には殺菌灯を利用している病院も多く見られたが、大きな効果が得られなかったのか、現在ではあまり見ることができなくなったのにだ。
それではなぜ、今の時代に殺菌灯なのか。
殺菌灯が注目される理由はアメリカにある。
現在,米国のサーベイランスシステムに,急性期患者集団におけるすべての医療関連感染症の負荷を単一で推定することができるものはない.われわれは,急性期病院における医療関連感染症の有病率を明らかにし,全米における医療関連感染症の負荷の最新の推定値を算出するため,地理的に異なる 10 州において有病率調査を行った.
https://www.nejm.jp/abstract/vol370.p1198
そして、オバマ米政権が抗生物質の効かない薬剤耐性菌による被害を5年間で大幅に減らすための行動計画を策定した。
米、耐性菌被害5年で削減/オバマ政権が対策強化
http://www.shikoku-np.co.jp/national/medical_health/20150327000236
さらにCDCはサイトでこのように述べている。
・患者の部屋の表面に関連する伝達事象を理解する
2011年には722,000件の医療関連感染症が発生し、入院時に約75,000人のHAI患者が死亡しました。手指衛生のような伝統的な感染対策努力に引き続き重点が置かれていますが、患者の病室の清潔さを改善することで、どれくらいの感染が予防できるかは不明です。患者の部屋の表面が伝達事象にどのように寄与しているかを理解することによって、どの表面が汚染される可能性が最も高いかを施設が把握し、これらの表面の洗浄と消毒を最適化することができます。・清潔度を測定する
表面をサンプリングしてその清浄度を測定するための多くの方法が存在する。環境汚染が医療関連感染のリスクに及ぼす影響を評価するために、清浄度を測定するための標準化されたアプローチが必要です。これらの方法を標準化することにより、将来の研究では、一定レベルの清浄度が改善された患者の安全性と関連しているかどうかを評価することができる。・プロセスに焦点を当てて清潔度を向上させる
環境サービス(EVS)労働者の重要性が会議を通じて議論された。病院の部屋を適切に清掃し、消毒する環境サービスの能力を妨げる要因は数多くあります。ラウンドテーブルは、EVS労働者の教育訓練方法、浄化と消毒の監視方法、EVSの仕事への構造的挑戦を含む、さらなる調査と指導が必要な分野について議論した。
https://www.cdc.gov/hai/research/eic-meeting.html
こうした背景が殺菌灯への関心を高めている。
着目すべき殺菌灯の使用方法
殺菌灯が注目され、結果を出しつつあるのには理由がある。
それは殺菌灯の使用順序を明確にしていることだ。
『患者が部屋を出た後、従来の手作業による清掃がおこなわれたのち、殺菌灯を使用する。』
テルモとXenexのサイトでは次のように説明している。
『通常、医療機関における環境表面の殺菌は、清掃スタッフにより手で行われていますが、拭き残しの発生や薬剤耐性菌への効果が薄いことが課題とされています。
細菌に紫外線が照射されると、細胞内のDNAが二量化反応、水和反応、分解などを起こし、死滅するといわれています。従来の手による環境殺菌後、病室内に満遍なくキセノン紫外線を照射することで、院内感染※の原因となる薬剤耐性菌やエボラウイルス、ノロウイルスなどの殺菌が期待されます。』
https://www.terumo.co.jp/pressrelease/detail/20170106/271
『Xenexロボットは、手作業による洗浄プロセス中に見逃される可能性のある微量細菌を破壊する』
https://www.xenex.com/resources/news/xenex-expands-relationship-with-terumo-lightstrike-germ-zapping-robots-now-available-in-singapore/
いずれも手作業による清掃後に存在する病原菌を殺菌する目的で使用するとしている。
この殺菌灯の使用順序は私が調べた他社製のものも含めて全て共通していた。
だが、初めに殺菌灯で消毒し、その後に従来の手作業による清掃でもよいように思える。
なのになぜ、この順番なのか?
手作業による環境表面の拭き残しなら、ほかにも対応方法はあるだろう。
清掃後に殺菌灯のようなノータッチ消毒に頼らなくてはいけない理由は『清掃そのものが不衛生なため』だからだ。
現在行われている病院内清掃は、清掃=清潔 ではなく、清掃=きれいに見せることでしかない。
『消毒剤で清掃しているから清潔になっているはずだ』と消毒剤を過剰に信頼し過ぎている。
それでは清掃の何が不衛生なのかを簡単にまとめてみた。
- 拭くたびに埃や汚れを雑巾に蓄積させる(その埃や汚れには病原菌を含む細菌が多く含まれる)
- よって雑巾に付着した菌や汚れが高密度になる
- 埃や汚れは移動性が高い
仮にICUの一つの個室の清掃を例に考えてみる。
清掃が終了した一枚の雑巾には多くの埃・汚れが付着する。時には雑巾を裏返しにして清拭するだろう。
最終的にその部屋の医療機器・備品類全てを清拭した雑巾はどれほどの埃・汚れが蓄積したか。
清掃前までには部屋中に満遍なく散っていた埃や汚れ、そして病原菌・細菌を一枚の雑巾に集めることになるのである。
病原菌・細菌が満遍なく散っている分にはそれほど衛生的に脅威ではなかった。
しかし、埃や汚れを一枚の雑巾に集めたことで、それは高密度の病原菌・細菌で汚染されたことになる。
そのような雑巾で清拭した医療機器・備品類は果たして清潔といえるだろうか?
また、その雑巾を扱っていた手袋にも、どれほどの汚れが蓄積したか。
そのような汚れた手袋で環境表面に触れ、埃や汚れを再付着させてしまうのだ。
埃ゆえに移動性は高い。触れただけで簡単に不衛生にしてしまうのである。
また、床を清掃するためのダスタークロスについても同様だ。
特に床は垂直面な壁や備品と比べて埃が自然に蓄積しやすく、病原菌・細菌が多いと思われる。
床の埃や汚れの扱いには、医療機器・備品の埃や汚れ以上に注意を払わなければならない。
現在一般的におこなわれている医療機器・備品や床の清掃は、埃や汚れを集めるという方法だ。
清掃員は院内感染の危険度が高い雑巾やダスタークロスを使用して、清潔であるべきところを清掃しているのだ。
そして残念なことに清掃が終わったその部屋を見て、きれいになったと思ってしまう。
ただ単に見た目がきれいになっただけで、一部の病原菌・細菌は雑巾へ、一部の病原菌・細菌は環境表面上を移動しただけ。
だから、手作業による清掃がおこなわれた後に、ノータッチ消毒である殺菌灯を使用しなければならないのである。
手作業による清掃には、知らず知らずのうちに『環境表面を不衛生にする』という要素があることを理解していなければならない。
それでは病院内のような免疫力が低下した患者がいる部屋を、清潔にするための正しい手作業による清掃方法はあるのだろうか?
私はないと考える。
現在の段階では、清潔にするための手作業による正しい清掃方法は確立されていないのである。
だから、殺菌灯が必要なのだ。
まとめと簡単な院内感染対策
最後に殺菌灯を購入できない中小病院はどのような院内感染対策を講じれば良いのか。
Xenex社だけでもアメリカを中心に400もの病院・施設で使用されている。ほかの殺菌灯メーカーの数を含めるとかなりの数だろう。
価格が1台あたり1千万円以上もするのにだ。結果として購入する多くは大病院になる。
そこで、中小病院のための簡単な院内感染対策を5つほど挙げてみた。
実際に試してみて、効果があったなら正規にマニュアル化し、より徹底しておこなうことで院内感染も減少するだろう。
1.埃や汚れを集めない方法で医療機器や備品を清拭することは実際には難しいだろう。
私は2度拭きを推奨する。一通り清拭した後、新しい手袋・雑巾に交換し、また初めから清拭するのである。
2回目に使用した雑巾もまた埃や汚れが付着するが、2回で大丈夫であろう。
床面についてはダスタークロスは使用すべきでないと考える。
一部分わずかな床でさえ、医療機器や備品と比べてはるかに不衛生だ。しかし、床そのものが不衛生であっても移動性が低いため、それはあまり重要ではない。そうではなく、床の表面上に存在する埃や汚れが不衛生なのが問題なのだ。特に床の埃の不衛生さと移動性の高さに着目し、それに関連するシューズ・シューズカバー・スリッパ・フットスイッチ・ダスタークロス・ちり取り・掃除機・キャスター・電気コード・チューブなどに付着した埃に注意しよう。
2.ベッドやストレッチャーに付属している電気コードや医療チューブを床に接触させてはいけない。特に検査や手術室に行くときに、電気コードや医療チューブを床に接触させていると、ベッドやストレッチャーが移動した分だけの床の埃がそこに付着してしまう。床の埃の不衛生さは上記に述べたとおりである。
3.いろいろな病院の院内感染対策が「ハイタッチ面(頻繁に触れる面)をよく消毒しましょう」と述べているが、それは誰のハイタッチ面かということを考えなければならない。医師や看護師だけのハイタッチ面と捉えてしまうと効果がでにくいであろう。優先して消毒すべきハイタッチ面とは【患者・医療従事者】と【清掃者】の2つの交差するハイタッチ面だ。【清掃者】は、時には清掃の過程で非常に不衛生な手袋で環境表面に触れる可能性があることを考えると、ハイタッチ面だけでなく、一度でも触れたところは消毒すべきではないか。手袋を交換しない清掃者はハイリスクなのである。
4.清掃者の手袋を5分毎・10分毎など、定期的に交換させる。
清掃者の手袋は汚れていることが多いが、常に汚れ作業に従事しているため、手袋の交換のタイミングが難しい。手袋を交換しようとしてもまた次に汚れ作業があるため、手袋の交換をせずにずっと同じ手袋で作業してしまうことがある。そのような手袋で、時には清潔であるべき環境表面に触れてしまうこともあるであろう。決められた時間で手袋の交換を促し、不衛生な手袋で作業し続けるのを強制的に止めさせる。この対策で効果があったなら、今までの交換するタイミングが間違っていたことになる。
5.全ての清掃用具を最低1日に1回は消毒する。
清掃に関連する道具は病院の中でも一番不衛生な物だといっても過言ではない。しかも通気性の悪いところに配置してあり、細菌の温床になりやすい。モップの柄のような頻繁に汚れた手で触れるところは一部屋清掃するごとに消毒したほうがよい。
一番後回しになりがちな清掃者・清掃道具に重点を置くことで、院内感染対策の結果が変わる可能性がある。
アメリカでは、殺菌灯を業務管理している多くは清掃担当者だという事実からも、殺菌灯照射は清掃の一部だと考えることができる。
院内感染対策が現在まで思うように結果がでなかった要因には、清掃というものがあまりにも関心を持たれなかったためと言えるのである。